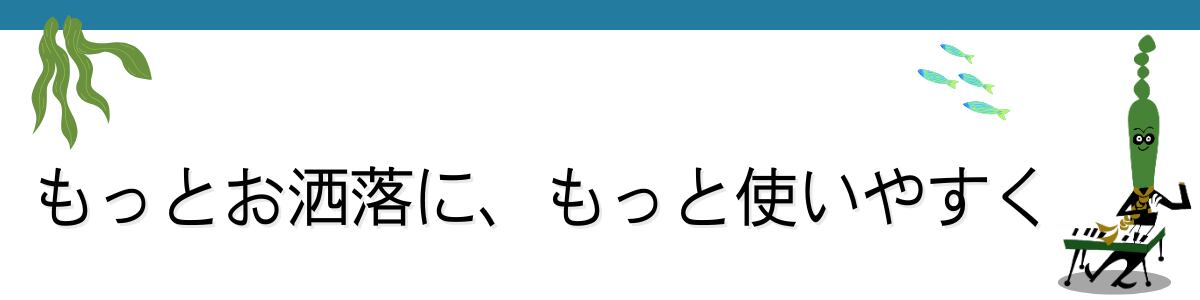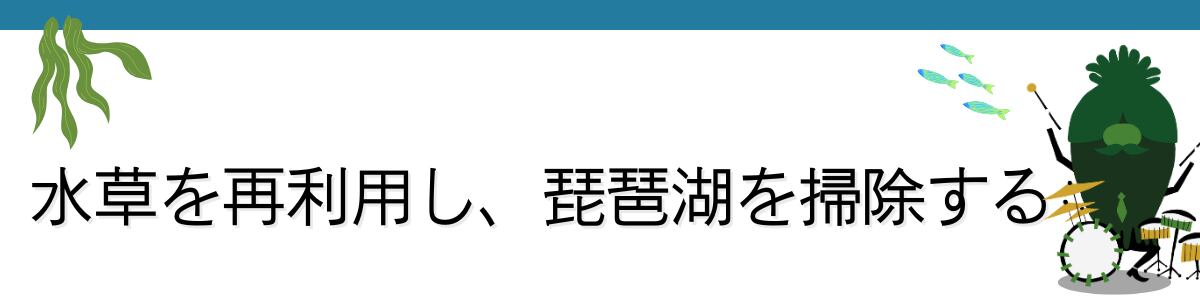「湖の恵」誕生の物語
オーガニック肥料「湖の恵」と植物活力液「プランツプラス」
「湖の恵」誕生の物語とは、単なる製品の紹介ではない。
背景にある思想と人々の意志、その全ての結晶だ。
原料は琵琶湖の水草、伊吹山系の間伐材、近江米の米糠と酒粕。
さらに近江北部の里山に由来する天然土壌菌。
これらを基に作られた100%植物性のオーガニック肥料と植物活力液。
「湖の恵」も「プランツプラス」も、滋賀の風土そのものを凝縮した存在だ。
だが、素材の羅列だけでは「湖の恵」は語れない。
「なぜ作ったのか?」「誰がどんな想いで携わったのか?」「その先にどんな未来を描いているのか?」
この物語が重要だ。
我々「THE COMPOSTS」は、その全てを音楽のように紡ぐ。
さぁ、セッションの始まりだ。
最後まで聴き、感じ取ってくれ。
「母なる湖~マザーレイク~」
滋賀県民や関西圏の者ばかりか、全国の人々に愛されておる琵琶湖。
しかし、近年『増えすぎた水草』の問題が深刻化しておってな、まずはそこから話そうかの。
水草は琵琶湖に棲む多くの生き物にとって、『生命のゆりかご』であった。
おぬしら人間どもも、水草が育んだ湖魚を大切なる食糧としておったし、かつては刈り取った水草を堆肥として農業に活用しておったのじゃ。
しかし、湖水の富栄養化や度重なる渇水の影響により、今や水草は異常に繁殖し、生息地域を広げておる。
増えすぎた水草が枯れ、腐敗すると、水質が悪化し、環境変化に敏感なる在来種が死滅してしまう。
そして、環境変化に強き外来種が勢力を伸ばすという、誠に嘆かわしき構図となっておるのじゃ。
滋賀県の対策にて、年間六千トン以上の水草が刈り取られ、揚陸され、堆肥化されておる。
されど毎年膨大な量が揚がるゆえ、減容化して無償配布するに留まるのが現状じゃ。
本来はもっと価値高きはずの琵琶湖の水草が、今では『厄介者』扱いされておるのが悲しゅうてならぬ。
そして「この現状を変えたい!」と立ち上がったのが、『湖の恵』じゃったのじゃよ。
あぁ…この「厄介者」とされた琵琶湖の水草を、どう扱うべきか
──その問いはまるで深い霧の中、朧げに揺れている夢のようなものでしょう?
結論はひとつ、水草を「良質の堆肥」へと紡ぎ変え、地上でたっぷりと「消費」されること。
「水草の恵み」は、まるで命の詩のように「大地の恵み」へと移ろい、資源の輪廻を織りなすのです。
そこで心に灯ったのは、「真に価値あるオーガニック肥料」を作り出すこと。
ただ大量に高速で分解するだけのプラントは、安価さを謳うがゆえに、魂を宿さぬ偽りの歌のよう。
「本当に良いもの」でなければ、誰もその響きに耳を傾けはしないでしょう?
また、大型プラントは大いなるエネルギーを消費し、CO2を吐き出す。
琵琶湖の環境を守ろうと誓いし者が、またもや環境を傷つけるとは、まるで詩の破綻のように悲しい。
だからこそ、関わるすべての者を満たす「三方よし」の調和こそが求められるのです。
そこで、選ばれしは良質な天然土壌菌を使い、発酵熟成させる伝統の「ぼかし堆肥」の技術。
鮒ずしや日本酒、漬物、味噌、醤油…滋賀の豊かな発酵文化が織りなす滋賀の智慧の結晶。
ただの製法ではなく、魂を込めて「良きもの」を作ろうと願ったその思い。
そうして、幾度も重ねられた研究と実験の果てに、エシカルで高品質な「湖の恵」が生まれたのです
──まるで悠久の詩の完成のように。
オーガニック肥料と聞くと、どうしても「なんだか臭いのでは…?」と感じてしまう方が多いのではないかと思いますの。
確かに園芸店の肥料売り場には、独特の匂いが漂っておりまして、苦手に感じる方も多いでしょうね。
ですから「湖の恵」は、落ち葉の下の土のような、やさしくて心地よい香りを目指して、原材料を厳選したのですわ。
琵琶湖の水草、伊吹山系の間伐材、そして近江米の米糠と酒粕。
そこに加えるのは、近江北部の里山に住む土壌菌を自社で培養した発酵促進材。
独自の嫌気的発酵技術を用いて、三ヶ月以上かけてじっくり熟成発酵させますの。
この土壌菌たちが、まるでふわふわの落ち葉を懐かしい香りの良い土へと生まれ変わらせてくれるのです。
まるで幼い頃に嗅いだあの優しい「土」の香りでございますわ。
そうそう、熟成が不十分だと未分解の成分が残り、酪酸や乳酸の匂いが混じることがあるそうです。
ですから、配合比率や攪拌の頻度を繰り返し調整し、発酵温度を60℃以上に保つことに成功したんですの。
数年にわたる試験を経て、ついに「嫌な匂いがしない堆肥」が完成したのでございます。
しかも、この努力は「湖の恵」に思いもよらぬ副次的な効果をもたらしているのですわ。
厄介者扱いされてた水草を、里山の土みたいな香りのする堆肥に変えた湖の恵の土壌菌。
こいつはただの土壌菌じゃなくて、酸素がなくても土の中で働ける偏性嫌気性菌ってやつなんだ。
おっと、難しい話だと思ったか?まあ、ちょっとだけ我慢しろよな。
堆肥ってのは土をフカフカにするために入れるもんだ。
でも、酸素が好きな好気性菌が作った堆肥は酸素がない土の中じゃ働けねぇ。
だから土壌改良効果は弱いってわけだ。
でも「湖の恵」の土壌菌は、積み重なった状態で嫌気的に働く偏性嫌気性菌。
固くなった土に撒けば地中深くまで入り込んで、土をふっくら蘇らせるんだぜ。
しかも水草、間伐材、米糠、酒粕を分解してるから栄養たっぷりで肥料成分も豊富だ。
窒素やリン酸、カリウムだけじゃなく、腐植酸のフルボ酸やフミン酸も多い。
黒い色は腐植酸の証拠だぜ。
要は肥料と堆肥のハイブリッド、それが「湖の恵」ってことだ。
これで土と植物の力をグイッと上げるんだぜ!
あ~「湖の恵」ってサラサラで使いやすいし、臭いも全然ないじゃん?
パッケージも超オシャレで、リビングとかオフィス、ショップに置いてても超イケてるんだよね!
観葉植物の隣にポンっと置いて、使いたい時にパパっと使えるのがめっちゃ便利だよね。
でもさ、もっと気軽にさ、計る手間とかなくて、いつでも使えて、究極にラクなのが欲しいじゃん?
理想は手も汚さずに片手で、スプーンとかも要らなくて2秒で使える感じ!
そんな思いから生まれたのが、植物活力液「プランツプラス」なんだよね。
いや、正直言うと「もったいない精神」が発動して、発酵中に出る水草エキスと土壌菌たっぷりの抽出液を捨てるのは超もったいないってなって、「よし、液体肥料作ろう!」って話になったんだ。
二次発酵で肥料成分はほぼ消えちゃったけど、フルボ酸やフミン酸、有機酸、コリンみたいなビタミン的な成分がめっちゃ入った活力液ができたんだよね。
その結果、季節も植物の種類も関係なく、弱った植物に元気をくれる超万能な資材が誕生!
「もっと手軽に」と「もったいない」が合体した奇跡、それが「プランツプラス」なんだ!
えっと…どれだけ「効果が高い堆肥」を作ったとしても、やっぱり使ってもらわなきゃ意味がないんだよね…。
例えばだけど、ベタベタしてたり、すごく臭い肥料だったら、どんなに効果があってもボクだったらちょっと使いたくないかなって…。
だからこそ、使う人の立場になって商品を作ってるか?っていう視点がすごく大事だと思うんだ。
ハゴロモモンさんが言ってた「嫌なニオイがない」っていうのは、きっとすごく重要なポイントだよ。
家の中でも、ベランダでも、花壇でも、ニオイが無い方がやっぱり安心だし、コバエとか虫が寄ってきにくいのも嬉しいんだよね。
あと、粒が揃ってると撒くときにムラになりにくいし、見た目も綺麗だから良いと思うんだ。
だから、インドア用の「湖の恵」って、粒の大きさを調整するだけじゃなくて、加熱処理もしてるんだって。
雑草の種や虫の卵を除去してるから、安心して使えるんだよね、
これってけっこう大事だと思うんだ。
あとは…ネジレモンさんも言ってたけど、パッケージのデザインがオシャレっていうのもポイント高いんだよ。
だって、普通の肥料袋って「ザ・肥料!」って感じで、正直お部屋に置きたくないじゃん。
だから、植物の隣に置きっぱなしでも違和感がないデザインって、実は結構大事なんだと思うんだよ。
色んなライフスタイルの人にも使ってもらえるようにって、そういう想いが詰まってるんだと思うんだよね。
どれ…もう一度「湖の恵」のモノづくりについて語らせてもらおうかね。
実は、「湖の恵」は発酵が終わった後の堆肥の製品化、これをすべて手作業でやっておるんだよ。
え?そんな手間のかかることを?と思うかもしれんが、これにはちゃんと訳があるんだ。
その理由のひとつが、琵琶湖に漂うプラスチックごみの問題なんだな。
原料の水草には、レジ袋や弁当の容器、ペットボトル、釣り糸、不織布マスク…実に色々なプラごみが絡みついておってね。
これがまぁ、10tダンプ1台分の水草に対して50L程度…って、数字だけ見ると少なく感じるかもしれん。
だが、これが本当に厄介で、プラごみは堆肥と比重がほぼ同じ。
だから機械では分けられんのだ。
篩を通して、一つ一つ、目視で取り除くんだよ。
大きなごみは見つけやすいが、小さなものは忍耐が要る。
こうして集まったゴミを分別処理するたびに、ワシらは琵琶湖のプラ汚染の深刻さを痛感するんだ。
水草を堆肥にしつつ、琵琶湖のゴミも掃除する。
まさに「湖の恵」は、湖と人の未来を繋いでいるんだよ。
あたしね、みんなにどうしても伝えたい「湖の恵ファミリー」の大切なお話があるの!
実はね、「湖の恵」の全商品は、長浜市にある「就労継続支援B型事業所」の皆さんが袋詰めしてくれてるのよ✨
そこに通ってる方たちは、いろんな事情で普通の仕事が難しかったり、今は働かない選択をしてたり。
でもね、「自立したい!」っていう前向きな気持ちを持ってて、日々チャレンジしてるの!
そんな皆さんに、「湖の恵」が、就労の訓練や機会を提供してるってわけ!
得意なことも人それぞれで、シール貼りが得意な人、力仕事が得意な人、正確な計量が得意な人…みんなの力を活かしてるのよ💪✨
週1回、2時間くらい工場に来てもらって一緒に作業するんだけど、これがすっごくいい刺激になってるんだって!
閉じた空間だけじゃなくて、実際の企業で働くことってすごく大切なことなの。
それに、自分たちが作った商品が全国のお店やお客様に届くって、やっぱり嬉しいよね♪
みんながお互いを認め合える優しい社会、その一歩が「湖の恵」なのよ😊
「琵琶湖の水草を堆肥にしている」と聞いて「良いリサイクル活動ですね!」などと言う輩がいる。
感謝はするが、はっきり言おう。
それは違う、甚だ遺憾である!
「湖の恵」は、廃棄物の再利用ではない!
水草を「資源」として購入しているのだ。
リサイクルとは、不要になったゴミを価値あるものに変える行為。
立派ではあるが、水草をゴミ扱いして良いものなのだろうか?
今こそ問おう!
「琵琶湖の水草は本当にゴミなのか!?」
否!資源だ。
「湖の恵」は水草を購入し、そこからビジネスを興し、収益を得ている。
このモデルが「水草=資源」という新たな価値観を生むのだ。
「偽善か?」そう思う者もおるだろう。
「湖の恵」が年間買い取っている水草は200t、全体から見ればほんの僅かだ。
されど、「湖の恵」が道を拓けば、いずれ多くの企業が水草活用に動き、「経済の循環」が生まれる。
それが真の戦略であり、「湖の恵」の使命なのである。
長かった「湖の恵」のストーリーも、いよいよフィナーレだ。
「THE COMPOSTS」の面々がそれぞれの想いを存分に語った。
私からは、ただ一言、総括しよう。
「購入して使う。それだけで琵琶湖が美しくなる」
これに尽きる。
「湖の恵」は水草を資源として購入し、堆肥化し、売上の一部を琵琶湖の環境保全に寄付している。
複雑なことは不要だ。
ただ使えば、琵琶湖が少しずつ、確実に美しくなる。
しかも、活きた土壌菌が土を蘇らせ、植物は生命力に満ちる。
エシカルで、地球・植物・人間に優しい肥料。
それが「湖の恵」だ。
さぁ、セッションを始めよう。
「湖の恵」で、君の大地を奏でてくれ。
水草の恵みを、大地の恵みに奏でようぜ!